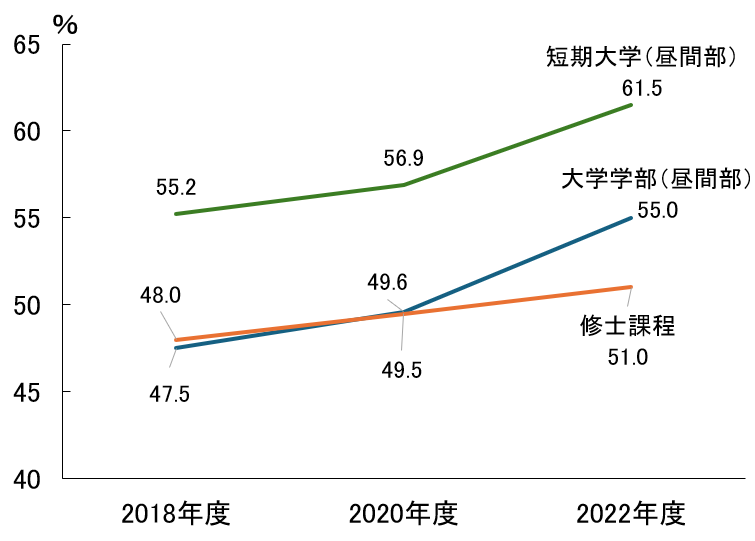お江戸日本橋の再生なるか
=民間資金活用の歴史に学べ=
半世紀以上の長い年月を経て、東京・日本橋から青空を見上げる日がやってくる――。
7月21日、国土交通省と東京都は、周辺のまちづくりと連携して、日本橋の上を覆うようにして走る首都高速道路を地下に移設する検討に入ると発表した。地下化するのは、竹橋と江戸橋ジャンクションの間の約2.9キロの区間。2020年の東京五輪後の着工を目指すとしている。
日本橋の上空を首都高が覆ったのは前回の東京五輪の前年にあたる1963年。急ピッチでインフラ整備を進める中で、用地買収の時間やコストを圧縮するため、日本橋川の流路に沿って高架工事を施す案が強行された。建設当初から景観が損なわれたことが問題視され、これまでに何度も見直し案が浮上した。2006年にも、当時の小泉純一郎首相の私的諮問機関が地下移設の提言をまとめたが、首相退任により実現しなかった。ここに来て急展開を迎えた背景には、完成から50年以上が経過した首都高が老朽化し、更新の時期を迎えていることがある。
日本橋の上にまたがる首都高
横から見た日本橋
日本橋の歴史と由来
日本橋が初めて架設されたのは江戸開幕の年である1603年。その翌年には、全国へ通じる五街道の起点と定められた。当時は、「お江戸日本橋」と呼ばれ、全国からの旅人が絶えず往来し、大いに栄えた。橋の北側には魚河岸(魚市場のある河岸)が広がり、日本橋川を多くの船が行き交った。南詰には、幕府の法度などを公示する高札場や罪人の晒(さら)し場が置かれ、幕府統治の象徴的な場所でもあった。日本橋には、交通、流通、行政、情報といった都市機能が集積していたのである。
しかし、明治以降は日本橋にとって受難の時代となった。1872年(明治5年)に新橋と桜木町の間に日本初の鉄道が開通すると、交通の起点としての存在感は徐々に薄れていった。東京府庁舎完成、東京駅開業によって丸の内地区が台頭、関東大震災で壊滅した日本橋魚河岸は築地に移転し、日本橋界隈に集中していた都市機能は分散した。
高札場跡に建つ日本橋由来記念碑
日本橋魚河岸市場発祥の地の記念碑
地下化の課題は「巨額な事業費」
現在、日本橋周辺では民間主導での再開発が進められており、国家戦略特区のプロジェクトとしても提案されている。首都高の地下移設による景観の改善と周辺環境の整備が一体で進めば、観光やビジネスの新たな拠点として、日本橋が再興することも可能だ。
問題は巨額な事業費である。小泉首相時代の提言書では地下化の費用は4000億~5000億円と見積られていた。さて、これを誰が負担するのか。
明治初期、馬車が往来しやすいようにそれまでの反り橋から平行な西洋スタイルの木橋に架けかえられた。この時、民間の基金である「七分金積立」の一部が活用されたという。七分金積立とは、江戸時代に老中の松平定信の発案でできた基金制度。江戸の地主が負担する町経費を倹約し、倹約分の7割を町会所が積み立て、災害や飢饉の際の救済事業に活用したのだ。多額の積立金は、明治維新後の東京市の財源として引き継がれ、道路や橋梁の建設や営繕事業などインフラ整備に充てられた。
今回の首都高地下化事業でも、現代に合った形で、民間資金の活用に知恵を絞る必要がある。土地の価値が上がることで受益者となる地主(地権者)や民間の再開発事業者との連携は不可欠だ。用地の無償提供を求めたり、ビルの容積率を引き上げ、テナントビルの収益の一部を事業費に充当してもらうなどの方法が考えられる。くれぐれも、景観改善を隠れ蓑に、事業費削減の視点が軽視されるようなことがあってはならない。国民、都民の税金投入をできる限り抑制しながら、街を活性化し、次世代へと引き継いでもらいたい。
(写真)筆者
タグから似た記事を探す
記事タイトルとURLをコピーしました!